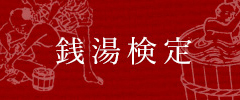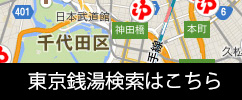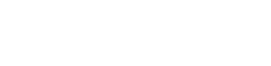東京都浴場組合理事長からの挨拶
東京都公衆浴場業生活衛生同業組合の理事長を務めております、石田眞です。私たちの公衆浴場業界は、長い歴史と伝統を持つ、健康と癒しの場として親しまれてきました。
銭湯は、日本の文化において特別な存在です。古くは江戸時代からその歴史が始まり、町の人々が集まり、日常の疲れを癒す場として親しまれてきました。銭湯は、街の中で人々が交流し、心温まるひとときを過ごす場でもありました。その歴史は、私たちの日本の文化を形作る一部として大切に守られてきました。この日本の古き良き文化はぜひ、外国の方々にも触れていただきたいと思います。
公衆浴場は、ただ入浴するだけでなく、健康増進にも貢献してきました。入浴による血行促進やリラックス効果は、心身の健康に大いに寄与します。また、入浴の際には、湯の温度や泉質による効能があり、様々な症状や疲労回復に効果があるとされています。公衆浴場は、私たちの心身のリフレッシュの場として、また病気予防や健康維持の手段として、多くの方々に利用されています。
私たち東京都公衆浴場業生活衛生同業組合は、この大切な健康文化を守り、発展させるために努力してまいりました。安全な環境と清潔な施設を提供し、皆様が安心して利用できるよう取り組んでおります。厳しい衛生管理とスキルの向上に努め、より良いサービスを提供することを心がけています。
しかし、私たちだけではなく、皆様方のご支援やご協力なしには、この文化を守り続けることはできません。私たちの銭湯文化を大切に思っていただき、公衆浴場をご利用いただくことで、この伝統を守り続けることができます。ぜひ、ご家族やご友人をお誘い合わせの上、公衆浴場へお越しください。
今後も、私たちはより一層の向上を目指し、より快適で安心して利用できる公衆浴場の提供に努めてまいります。
最後になりましたが、私たちの公衆浴場業界が、皆様の健康と癒しの場として一層の発展を遂げることを願い、皆様のご健康と幸せを心からお祈り申し上げます。
東京都浴場組合理事長 石田眞